
以前、介護予防の窓口という記事を書きました。
なるべく早く地域包括支援センターに相談して、できるだけ要介護になることを予防したいものです。
要介護状態ではなく再び自立することが理想です。
とはいえ人は誰しも歳を取るし、急に病気になったり怪我をして要介護状態になることは万人に訪れることです。
自分の意に反してこうなってしまったら、やはり早めに認定を受け、サービスを受けることをお勧めしたいです。
サービスを受けることで、それ以上の悪化を予防もしくは自立へ向けての改善が期待できるからです。
またサービスを利用することで介護する側にとっても負担が軽減されます。
もちろん第3者の手を借りることに抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょうし、介護保険に頼らんでも自分でなんとかする、という気概のある方もいらっしゃるでしょう😁
しかし、やはり早めにプロの手を借りたほうが近道だと思います。
どうか遠慮なく人の手を借りましょう!年々値上がりする、高い保険料も払っていますし😁
要支援の認定(1,2)を受けた方は地域包括支援センター、要介護の認定(1〜5)を受けた方は居宅介護支援事業所というところがサービスのコーディネイトをお手伝いしてくれます。
利用したい具体的なサービスがあればお願いしても良し、提案してもらったサービスを使うのも良しです(どんな介護サービスがあるかはまた別の記事にする予定です)。
介護の窓口
前述の通り、介護度には要支援1,2要介護1,2,3,4,5と7段階あります。
要支援1が最も軽く、要介護5が最も重い介護度です。金銭的にも要介護5の方がたくさんサービスが使えます。
世帯の収入額によって1割〜3割と自己負担はありますが、要介護5で月々362,170円までのサービスが使えます!
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/shikyu-gendo.html
介護認定申請については役所の高齢介護課、介護保険課など(自治体によって微妙に名前が違っていたりします)に行き、申請します。
地域包括支援センターで相談したことがあり、何らかの支援を受けている方はまずはそこの担当者へ相談するのが良いです。
介護度が1〜5の場合は「居宅介護支援事業所(ケアマネージャーさんがいるところ)」というところが介護計画を立ててくれます。
どの事業所にするか決まっていればその事業所に直接依頼しても良いし、決まっていなければ市役所(介護認定を申請したところ)の方にお願いしたり、地域包括支援センターの方を通じて紹介してもらうこともできます。
またお住いの地域の居宅介護支援事業所は以下で検索できます。
職員の人数や現在受け持っている介護度の割合など、詳細な情報も確認できます。
ご近所で介護サービスを受けている方がいれば、ケアマネージャーさんの評判を聞いてみることをお勧めします。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
お住いの都道府県→介護事業所を検索→詳しい条件で探す→サービスの種類で「居宅介護支援」を選択
→事業所の所在地でお住いの市区町村を選択
→住まいから検索で郵便番号入力、住所自動入力し、事業所までの距離(5km範囲程度で良いと思います)を入力して検索してみましょう!
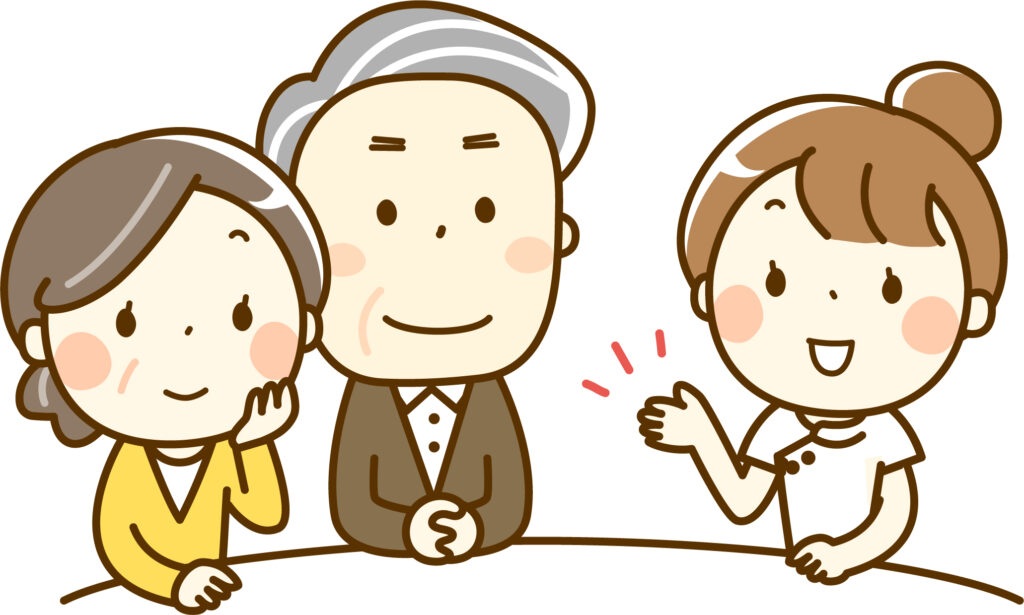
介護度決定までの流れ
役所で申請したら後日調査員がご自宅を訪問し、認定調査を行います。
どんな調査かと言うと、食事・排泄・入浴・更衣・整容・移動などの日常生活で困っていることや大変な介護の状態をご本人やご家族に聞き取り調査し、記録します。
この調査書類をもとに全国共通のコンピュータにかけ、介護度の1次判定結果がでます。
また主治医の先生が医学的意見書を作成します。
これら2つの書類をもとに専門家が集まって(介護認定審査会)判定会議が開催され、介護度の最終結果(2次判定結果)がでるのです。
申請〜介護度決定まで原則30日以内ですがそれ以上かかる場合もあります(認定調査票や主治医意見書の完成具合)。
あまりに待つようなら役所や主治医の先生に確認してみることをお勧めします。
ただ介護度が決まらないからと行ってサービスが使えないわけではありません。
介護保険証の有効期間は申請日からとなりますので、結果が出ていなくとも暫定でサービスが利用できます。
ただし、介護度によって限度額があるので、正式な結果がでるまでは必要最小限のサービスにしておいたほうが無難です。
ちなみに介護保険証の有効期間は新規では原則6ヶ月、介護認定審査会のさじ加減で3ヶ月や12ヶ月の場合もあります。
以降の更新では3ヶ月〜48ヶ月(48ヶ月ができたのは最近のことで、前回と状態が変わらない場合のみ設定可)。
大きな変化がない限り、24ヶ月か36ヶ月か48ヶ月の期間になると思いますが、状態がとても不安定な場合は3ヶ月になることもあると思います。
むー、複雑ですね。審査会の方に任せましょう😁
まとめ
- 介護度には要支援1,2要介護1〜5と7段階あり、要介護5に近づくほど介護が大変になり、サービス利用限度額が大きくなる。
- 要介護の方のサービスコーディネートは居宅介護支援事業所、要支援の方のサービスコーディネートは原則地域包括支援センター(地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託する場合あり)。
- 介護認定の申請窓口は市役所の介護保険課(高齢介護課など自治体により呼び名違いあり)。以前に地域包括支援センターで何らかの支援を受けたことがある方は、まずここに相談してみても良いと思います。
- 申請したらご自宅への認定調査→1次判定結果→認定審査会で判定会議→最終(2次判定)結果の流れで介護度が決まります。
- 介護度が決定するまでには申請〜約1ヶ月程度かかりますがサービスは暫定で利用できます。
- 事前に居宅介護支援事業所を検索したり、ケアマネージャーさんの評判など聞ける方がいれば確認しておくと良いでしょう !

